「上司や同僚との人間関係がつらい……会社を辞めたい」と感じている方は多いのではないでしょうか?
キャリア支援の仕事をしていると、「上司と合わないのが我慢できなくて、転職をしたいと思っています」という相談をよく受けます。確かに、人が上司や同僚などの他人に嫌な思いをさせられているケースは多々あります。
しかし、せっかく志をもって入社した会社を、たった一人の上司との相性で辞めてしまうのはもったいないと感じることもあります。
では、今の会社に残ると決めた場合、どのようにして人間関係のストレスを乗り切ればよいのでしょうか?
私自身も同じような経験をしてきました。その際に役立ったのが、「反面教師思考」です。
これは、嫌な経験をしたときに「自分は絶対にこうはならない」と強く決意し、その経験を自分の成長に活かす考え方です。本記事では、私が実際に活用した方法を紹介します。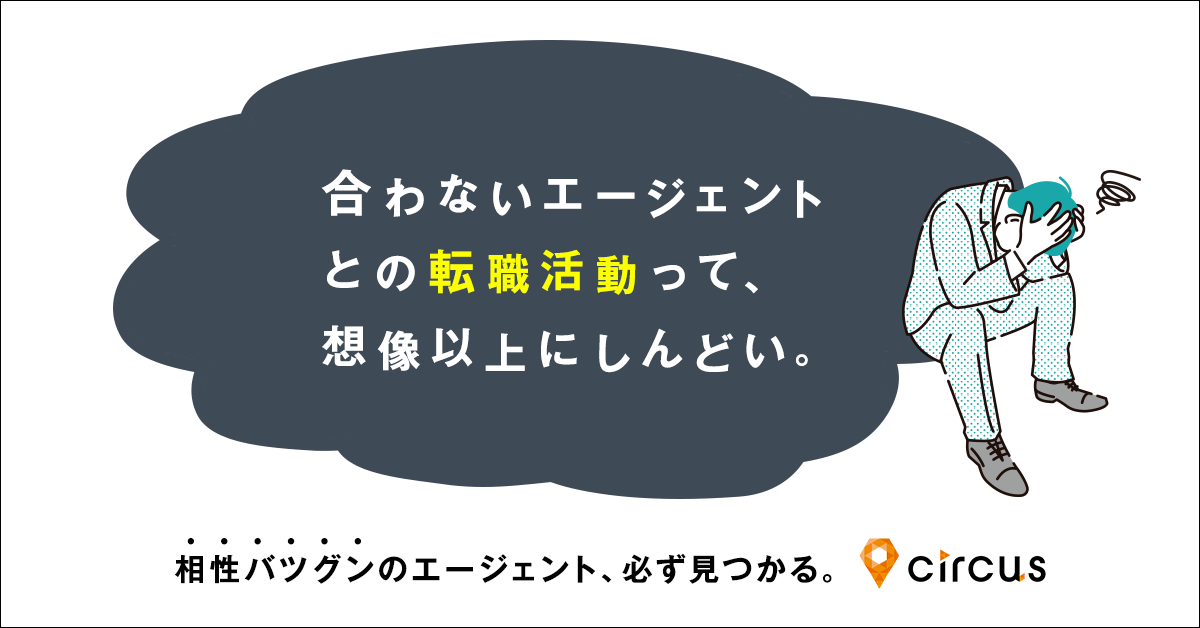
反面教師思考とは?
あなたは「反面教師」という言葉を聞いたことがありますか?これは、誰かの悪い例を見て「自分はそうならないようにしよう」と学ぶことを指します。
私自身も、過去の職場で理不尽な扱いを受けたり、ストレスを感じたりしたことが何度もあります。そのたびに「絶対に自分は同じようにはならない」と考え、行動するようにしました。
この思考法を身につけることで、人間関係のストレスをただの苦痛で終わらせるのではなく、自分の成長につなげることができるようになったのです。
私が実践した「反面教師思考」の事例。
「怒り」で人を動かそうとする人にはならない。
私の家庭環境では、父が仕事人間で家庭を顧みず、何かと「怒り」の感情を使って人を動かそうとする人でした。
私はこの点がどうしても許せず、自然と「自分は絶対に怒りで人を動かす人間にはならない」と決意していました。
結果として、今では周囲から「温厚な人」と言われることが多く、職場でも情緒的に落ち着いた対応ができています。これは、父の行動を反面教師にしたおかげです。
高圧的な先輩から学んだ「後輩への接し方」。
銀行員時代、私の隣の席には高圧的な先輩が座っていました。その人は常に怒り口調で指導をし、時にお客様の前で私を叱責することもありました。
そのストレスは想像以上で、業務中に全身に蕁麻疹が出るほどでした。その経験を通じて「自分が後輩を指導する立場になったら、絶対に同じことはしない」と私は決意しながら日々を過ごしていました。
結果として、後輩には丁寧に接し、わかりやすく指導することを心がけるようになったのです。
また、その先輩が周囲からも「あの人の言い方はひどい」と思われていたことを後になって知り、「自分が違和感を感じたことは間違いではなかった」と気づくこともできました。
同時に、「そう思っていたなら、一言声をかけてくれたらよかったのに」という思いも湧いてきたのを覚えています。私はこれも反面教師とし、困っている人がいたら声をかけるという心がけを持つに至りました。
「理屈と感情」を分けて考える。
人間関係に悩んでいるとき、多くの人が「感情」に引っ張られすぎてしまいます。しかし、感情だけで判断すると、冷静に考えれば学びになることを見落としてしまうことがあります。
そこで私が取り入れたのが、「理屈と感情を分けて考える」という思考法です。
具体的には、相手に言われたことを以下の4つに分類して整理しました。
- 理屈○/感情○
- 言われたことも正しく、言われ方も納得できる。 → 素直に受け入れる。
- 理屈○/感情×
- 言われたことは正しいが、言い方に納得できない。 → 無理のない範囲で、成長の機会と捉える。
- 理屈×/感情○
- 言われたことは間違っているが、言われ方は納得できる。 → 許容できない間違いの場合は、勇気をもって受け容れない。
- 理屈×/感情×
- 言われたことも間違っていて、言われ方にも納得できない → 適当に受け流し心の中で無視する。
特に「理屈○/感情×」のケースは、冷静に受け止めることが重要です。感情に引っ張られると、せっかくの学びの機会を失ってしまうからです。
嫌いな人に自分のキャリアを奪われないために。
「言われていることは正しいけれど、あなたに言われたくない。」「正しいのだけど、言い方がひどくて受け容れられない。」と感じることが、あなたにもあると思います。
その事象との向き合い方によって、自分のキャリアや成長の仕方が大きく変わってきます。
これを感情だけで処理してしまうと、論理的に正しいことを吸収できずに、自分の成長の機会が一つ減ってしまいます。これが繰り返されると成長の機会が失われ、極端な話、「内容の正しさも、言われ方も整っていないと成長できない人」に自分がなってしまうリスクもあるのです。
嫌な人に自分のキャリアを奪われるとは、こういう状態のことを言います。せっかく手にした自分のキャリアを、マイナスの感情で汚されるのは不本意ですよね。
だからこそ、出来事を理屈と感情で分けて考えることは大事です。
私もこれに苦労しました。しかし、その高圧的な先輩と同じことを別の上司から指摘されたときに「はっ」としました。「このままだと仕事ができないビジネスパーソンになってしまう……。」
そこから、言われた瞬間は感情が乱れても、後で冷静になって「言われた事実のみ」を考えることにしていました。「言い方」ではなく「言われたこと」に目を向けるように意識をするということです。
この思考を身につけてから、理屈・感情ともに成長の機会を逃さない意識が自分の中で定着しました。いきなり実践は難しいかもしれませんが、まず理屈と感情で分けることから始めてみてください。
でも、無理はしない。
反面教師思考を実践すると、「自分は」こうならないぞ!というように、自然と感情の矢印が自分に向きます。この時気をつけたいのが、無理をして自責にし過ぎることです。
反面教師思考は、自分の成長やポリシーの形成には役立ちますが、感情の面で限界を感じたり無理だと思ったら、ひとりで抱えずに相談をしましょう。転職や異動など物理的に環境を変えることも選択肢の一つです。
まとめ:辞める前に「反面教師思考」を試してみよう。
人間関係の悩みは、仕事をしている限りついて回るものです。しかし、その物事の捉え方、それに直面したときにパワーを向ける方向性は、自分で決めることができます。
「この人みたいにはならない」と決意し、「理屈と感情を分けて考える」ことで、今の職場にいる意味を見出せるかもしれません。
もちろん、どうしても耐えられない場合は転職も選択肢の一つです。しかし、「会社を辞めたい」と感じたときに、一度「反面教師思考」を試してみることで、辞めるべきかどうかの判断がよりクリアになるはずです。
よく、「嫌なことを与えてくれる人もありがたい存在だから感謝しよう」、というメッセージを目にすることがありますが、その考えは必ずしも必要ではないと私は思っています。
私はそこまでお利口さんにはなれません。嫌なことと向き合った事実と過去の自分に感謝できればそれで十分だと思います。
パワーを向ける方向を自分で決めて、あなたのキャリアを、嫌な上司や同僚に奪わせることなく、自分自身で切り拓いていきましょう!
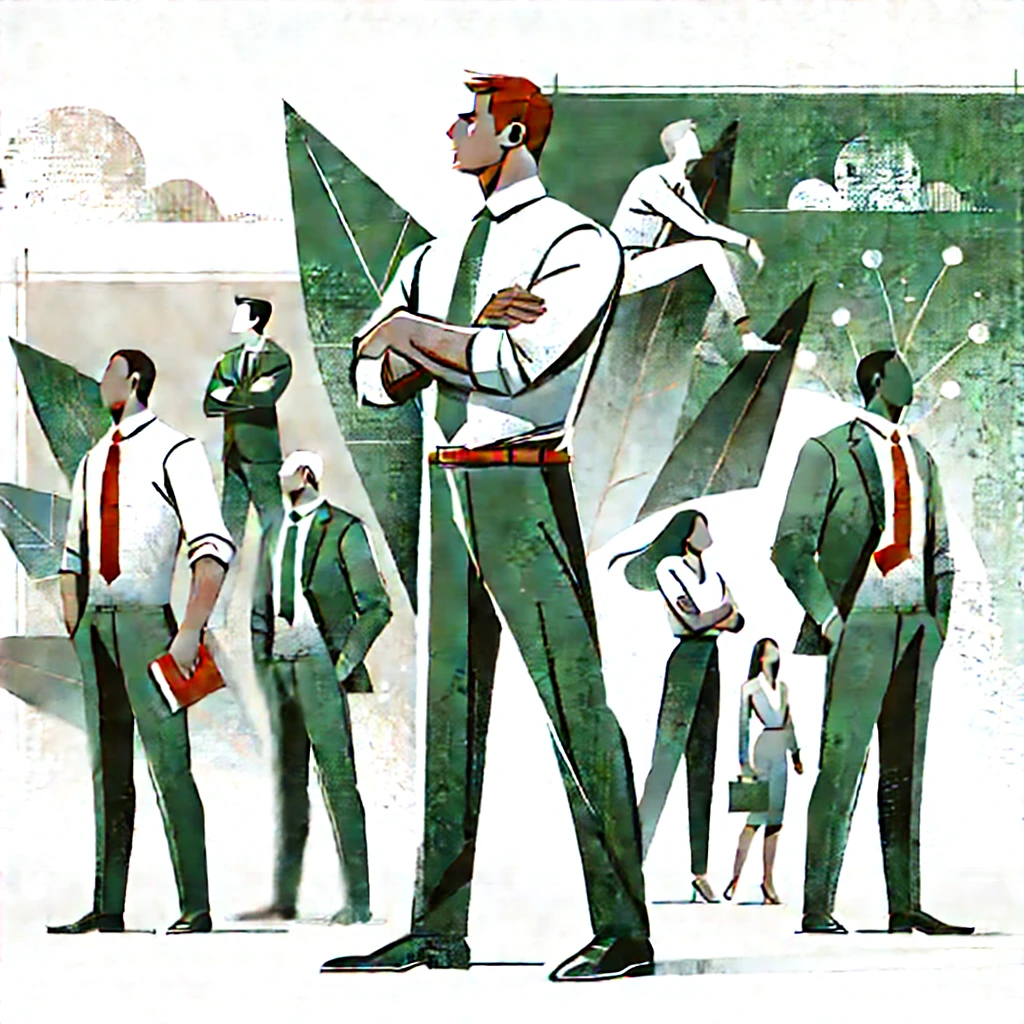


コメント