2025年9月、2級キャリアコンサルティング技能士(以下、CC2級と表記)に合格しました。今回の受験・合格は35歳の自分にとって、キャリアと学びの転換点でもあったと感じるので、文章として整理して置こうと思い、本記事を書いています。
もしあなたが、
- CC2級の受験を考えている
- 社会人の学びに興味がある
- 自分のキャリアについて考えたいと思っている
などの気持ちであれば、参考になると思いますので、ぜひ読んでください。
特に、「キャリアコンサルタント資格を取得してからしばらく時間が経過しており、養成講座の記憶がないところからスタート」という方には参考にしていただけると思います。
※各種、面談サービスを行っています。キャリアや仕事、学びや生活など、お話したい方は、ぜひ以下をクリックしてお申し込みください!
お話聴きます(おすすめ)
コーチングセッション
キャリアコンサルティング
バックグラウンド:学科が心配!ほぼ1からの学び直し
今回の受験に至るまでのバックグラウンドは以下の通りです。
- 2013年 キャリアコンサルタント養成講座に通う。講座終了時、社会人経験年数の不足でキャリアコンサルタントの試験を受けられず、しばらく塩漬け状態になる。
- 2019年 キャリアコンサルタントの試験を受け、合格する。
- 2024年 初めての資格更新を実施する。
- 2025年 職場で得たきっかけ(後述)からCC2級の受験を決意。養成講座のテキスト類は処分してしまっており、何もないところから勉強をスタート。
養成講座の受講からは10年以上、キャリアコンサルタント資格の取得からは5年以上が経過、実務経験はあれど本格的な学び直しが必要な状態でした。
ちなみに、受験を決意し、試験に向けて勉強した期間は3−4ヶ月です。
CC2級を受験を決めたきっかけ|自分のキャリア設計と専門性を示す必要性
きっかけは、勤務先での異動と自身のキャリア設計でした。
私は2024年に、キャリアアドバイザー(転職エージェント)から人事の部門へ異動をしました。人事の中でも社員のキャリア相談を受ける仕事をしています。
転職エージェントのキャリアアドバイザーではなく人事という帽子を被ってキャリア支援を行うことに変化したことから、キャリア支援者としての在り方を再構築する必要性を感じました。同時にキャリアコーチングの副業を始めたことも、その必要性を強くしたと思います。
勤める会社の業種柄、キャリアコンサルタントの資格を持っている人はたくさんおり、キャリア支援の実務経験がある人も多くいます。「今のあなたの仕事って現場のキャリアアドバイザーを連れてきて、やってくださいって言ったらできちゃう仕事だよね」という会話が先輩社員とあり、自分の在り方をどうすべきか、一種のアイデンティティ・クライシスに陥りました。
Kindleで自分の生い立ちから現在までについて書いたのも、そのきっかけからです。キャリア支援者としての自分がどこから形成され、今どういう状態にあるのか、改めて自分と向き合って本にしました。
(ちなみに著書はこちらです。よかったら読んでください!)

内省と自己理解を進める中で、ある程度の前進感は持てたものの、スッキリしません。自分のキャリア面談の幅や引き出しの狭さ、深まり方の不足、などの課題感と向き合う日々が続きました。
「これは学び直しが必要だな」という結論に至り、色々な方面の資格や講座などをリサーチした結果、キャリア支援者として生きていくなら、そのド真ん中で磨こうと思い、CC2級を受けることに決めました。
受験に向けてやったこと|環境・マインド編
合格が目標ではあるものの、学びそのものについてアップデートしたいという思惑もあり、以下のようなことを試みました。
1 24時間営業のジムに入会する
日々の学びをする中で、筋トレした後は集中力が高まって勉強するのに最適、という情報を耳にしていました。生活習慣を朝型にシフトしたいとも思っていたので、そのトリガーにする目的でジムに入会しました。
2 勉強に関する成功体験を捨てる
私の「勉強」における成功体験は大学受験です。高校3年生の夏から、野球部で鍛えた体力と根性だけを頼りに猛烈に勉強。通学や隙間の時間を駆使し、平日は学校の授業以外に5−6時間、休日は11−12時間の勉強漬けの毎日を送り、現役での合格を勝ち取りました。
この成功体験が、社会人になってからの自分に影響していたと最近になって気が付いたのです。
これまでの私は、資格を取ろうとすると、隙間時間をかき集めて「その資格勉強以外のことをしない前提で」日常の生活を設計し始め、それを実行すれば合格できるというシナリオを作って勉強をスタートしていました。
社会人であり、高校生の頃のような体力もなく、やるべきこと・やりたいことが拡散する自分にとって、このやり方が非現実的であるのは明らかでした。
しかし、大学受験での成功体験が呪縛となり、努力と根性をベースに試験勉強一点に集中して他のことはせずに打ち込む、「試験に受かるとはそういうものだ」という思考が自分の中に染み付いていたのです。
今回はこの思考を手放すことにしました。内省を通じて、そんなものが今の自分には不可能であることを知り、受け容れたのです。35歳になってようやく(笑)。
ということで、「勉強は休日の午前中4時間、追加でやりたいと思ったときはやる、それ以外はしない!」このルールで勉強することに決めました。
3 家族に宣言してジムからカフェへのお決まりルートで勉強する
休日の午前中はジムと勉強にすることを家族に宣言し、それを実行に移しました。早く起きて家族の朝食を用意してからジムに出かけ、筋トレが終わったらカフェの開店と同時に入りコーヒーを注文し、そこからずっと勉強する。カフェが自習室みたいな感覚でしたね(笑)。
合格に向けてやったこと|勉強編
座学のブランクがあった私にとって、学科試験が高いハードルでした。養成講座時代のテキストは処分してしまっているし、何より困ったのがCC2級は「過去問と正答番号は掲載されているが解説がない」という学習環境。過去問集も販売されていない中、以下のような勉強方法で臨みました。
1 市販のテキストを通読する
学科試験の体系的な勉強は、キャリアコンサルタント試験を受けた6年前にしたのが最後。どんな内容のインプットが必要なのか全体像を把握したいと思い、市販のテキストをざーっと通読しました。覚えようというより、全体を思い出す感覚です。
通読したのはこちらの本です。👇️
標準レベルの国家資格向けですが、全体像を把握するには十分な内容だったと思います。
2 3回分の過去問を解く|1周目
過去問学習のゴールは3回分の過去問について、「なぜこれが正解なのか分からない問題をなくすこと」に設定しました。
1周目は、現時点の実力で解いてみて、自信をもって正解できるものと理解が怪しい・分からないものに分類する目的で解きました。実務でもよく話題に上がる理論や倫理系の問題は1周目の時点で解けた記憶があります。
3 3回分の過去問を解く|2周目
2周目は、1周目で自信をもって正答を選べなかった問題を解きました。選択肢一つ一つについて、それが適当である理由・不適当である理由が分かっている状態が目標です。選択肢の誤りの部分に線が引けるようになることをイメージ。
ここが最も苦労したところです。2級向けの参考書もなければ過去問集もない。
私がとった方法は、各問題に記載されているキーワード(例:理論家の名前)や資料・制度・サイト名(例:能力開発基本調査・社会保険制度・jobtagなど)を起点に、参考図書を開く、各種サイトを検索して読むなどして該当箇所の記述を探し、それをもとに正誤の根拠を理解するというプロセスを踏みました。
ちなみに学科対策で使用した参考図書はこちらです。👇️
これが結構大変で、目当てのサイトに辿り着いても、選択肢の該当箇所を探すのに時間がかかる、目的の理論についての解説を見つけても選択肢に関する記載がない、などの壁にぶつかりました。なんとか探し当てられることが多かったのですが、どうしても見つからないときは、時間も限られているので探し当てることにこだわり過ぎず、次に進んでいました。
大変ではあったものの、この営みの過程で多くの制度資料や参考になるサイトに触れることができたのは、キャリア支援の中で引き出しが増えることにもつながりました。この点で収穫があったと思います。
4 3回分の過去問を解く|3周目
3周目は総仕上げの感覚です。2周目で正誤の判断は分かったものの理解が怪しい部分を中心に復習をしました。7割で合格の試験ですので満点を狙うようなことはせず、できる問題を確実に取れる状態に仕上げるイメージです。
5 1−4の過程でノートにまとめる
全体像の通読・過去問ベースの学習を進める過程で、「あ、これはこういう仕組みになっているんだな」と理解したものについては、ノートにまとめていました。書くことで覚えるというのは、科学的に効果が有るだの無いだのと情報が飛び交っていますが、私個人として科学的にどうかよりも自分が書かないと気持ち悪いタイプなので、都度都度ノートに書いていました。 最終的には、A5サイズのノートが1冊埋まるくらいの量を書きました。
6 実技の対策|論述編
論述対策は、3回分の過去問を2回ずつ解きました。自分なりの回答をノートに書いて、参考図書に書いてある論点と大きなズレがないかを確認する、という作業を行いました。参考図書が過去問のケースをそのまま扱っているわけではないので、単純比較はしにくいですが、論点を外していないかという視点で参考にしていました。
参考図書はこちらです。👇️
なお、時間を計らずに対策をしていましたが、試験本番では時間がギリギリで少々焦った記憶があります。早く確実に仕上げるための対策は必要だなと感じた次第です。
7 実技の対策|面接編
面接対策は、職場の同僚とロープレを行いました。これはとても助かりました!内容は、相互にクライアント役とコンサルタント役をやり、フィードバックし合うという一般的な対策です。
オンラインで実施したので、録画をして振り返りすることができました。これがとても役に立ちます。客観的に自分の面談を見ると多くの気付きが得られるのです。「うわ、展開遅っ!」「なんでそっちに話を持っていた?」「話したいのはそこじゃないだろ」など……。気付いた点を次のロープレで実践して、というのを繰り返すことで、合格へのイメージを構築していきました。
また、1級技能士の方がやっているロープレ動画(YouTube)もいくつか参考に拝見しました。自分と違う展開の仕方をする様子を見て、視野を広げられた感覚があります。
試験勉強に使った参考図書と資料
👆️ 上記2冊は参考になりますが、私のように学習のブランクがある場合、この参考書のみで「サクッと合格する」のは難しいと思います。試験全体を把握する位置づけで活用することをおすすめします。
👆️ 独立行政法人労働政策研究・研修機構のレポートです。各種理論の学習に大変おすすめです。これは大変有益な資料で、印刷して机に置き、実務でも活用しています。
試験当日から合格発表前まで|主に気持ちの変遷を軸に
学科試験当日は、気持ちが高ぶっているのを感じました。どちらかというとワクワクしていた記憶があります。ここまでやってきた勉強の方法や成功体験を捨てて臨んだ結果が、正解だったのか否か、もう少しで分かるのかーと思いながら試験会場に向かった記憶があります。
会場に着いてから、ちょっとだけ感情がピクッと動く瞬間がありました。知り合い同士の受験生がいたようで「今回あんまり勉強してないんだよねー」的な会話がされているのが聞こえてきて、それに対してちょっと憤りを感じたのです。「あ、熱くなっている自分」と悟って、試験後に会話のネタにしようなんてことを考えてやり過ごす。そんなシーンがあったのを覚えています(笑)。
学科試験が終わって、休み時間を経て論述です。意味がないと分かっていながら、学科の結果が気になって、解答速報がやっていないかなと検索する自分がいました。これは人間の性だなーと思います。そりゃ早く知りたいよね(笑)。
論述試験は前述の通り、思ったより時間の余裕がなく少々焦りました。試験が終わるときには気力が尽きており、しばしぼーっとしてしまい、会場を出たのは受験者の中で最後でした。夏だったのもありますが、ものすごくのどが渇いて水をギュッと飲んだことを思い出します。
面接試験は、シンプルに手応えがなかったです。苦手な展開だなと感じながら、なんとか具体的展開にまで至ったが果たして……という感じでした。
そんな手応えだったこともあり、試験終了から合格発表までの期間は、前向きに次の展開を考えるというより、他の勉強や取り組みに注力して、しばし現実逃避しているような感覚。早く結果を知りたいという気持ちが強くあったので、何かに取り組むことで少しでも時間の経過を早く感じたいと思って過ごしていました。
CC2級への挑戦で得られたこと
今回の資格への挑戦で得られたことは、大小様々あります。
本業であるキャリア支援者として得られたこと
熟練レベルである旨の資格を得ることができ、自信を一段深めることができました。面接試験も苦手なタイプの展開ではありましたが、そんな中でも一定の質を担保して面談を遂行できることが証明できたのは、私にとって意味ある実績となりました。
本業の面談実務にも変化をもたらせました。試験勉強を通じて面談が体系的に設計されていることを知り、基本的態度・関係構築・問題把握・具体的展開の流れで自身の面談を振り返ることで、アップデートや軌道修正すべきポイントを見出しながら業務を遂行するようになりました。結果として、内的な変化にとどまらず、行動を変容するクライアントが増えてきたように思います。
また、理論をはじめとして本格的に学び直しをしたことから、知識として得たものを面談の場で実践する機会も増えました。キャリア理論をフレームワークに落として活用する、理論の図を画面で見せながら思考を深めてもらうなど、理解・インプットなしにはできなかったことを試せるようになっています。
本業以外で得られたこと
勉強に関しての成功体験を捨てたことで、資格取得や学習に挑むことへのハードルが下がりました。これまで以上に積極的に様々な学びを実践できそうです。
同時に、朝ジムに通って生活習慣を整えたことで、健康面にも良い影響があったと思います。筋トレをするようになってから、日中に眠気が来ることが減りました。今まで、長距離ドライブの際にはコーヒーと休憩が必須だったのですが、今では終始スッキリした状態でいられるなど、体に変化が起きています。
また、勉強をするという制約を課したことで、それ以外のことがしたくなる意欲が湧きました。よく試験前は部屋を掃除したくなると言いますが、私の場合は読書をしたい欲が猛烈に襲ってきました(笑)。この受験期間を経て読書量がぐんと増えたと思います。
加えて、いつも通っているカフェの店員さんにも顔を覚えてもらって仲良く会話できるようになりました。これも試験をきっかけにした良い変化です(笑)。
これからの学び戦略 |型と力の両立を極める
キャリア支援者として仕事をしていこうと決め、CC2級に合格した今、これからの自分の学びを再設計しました。自己実現と学びについての内省は昔から絶えず行っており、あーでもないこーでもないと考えながら、アップデートし続けています。
今回は、主体(何として学ぶのか)と身につけ方の2つの観点で整理。いずれにしても、至高のキャリア支援者を目指して鍛錬していこうと思います。
主体による整理|何として学ぶか
学ぶ主体を、専門家(キャリア支援者)としての学び/社会人としての学び/人としての学びの3つに整理しました。

専門家としては、カウンセリングやキャリア支援、対人支援にまつわる情報・知識を学ぶこと。もちろん実践によるレベルアップも欠かせません。
社会人としては、BTC(Business/Technology/Creative)に分けてスキルを磨き、人としてはリベラルアーツに代表される教養やもう少しライトな雑学など、話していて面白い深みのある人物を目指します。
キャリア支援の仕事は、私自身が人生で経験したこと、学んだこと、すべてがその肥やしになる仕事だと私は認識しています。専門的な知識のみではなく、多くのことを学んで自分の知見として蓄積することで、キャリア支援者として熟していきたいと思います。
身につけ方による整理|型とポータブルスキル
専門領域における資格は「型」であると私は解釈しています。キャリアコンサルティング技能士であれば、キャリアコンサルティングの型を学びます。1級まで取得できればその型を高い次元で体得できているものと対外的にも示せるでしょう。
私は自分の専門領域であるキャリアコンサルティングについて、1級まで学んで型を習得しようと考えています。加えて、前職の金融でFP2級まで取ったので、せっかくならこれも1級まで取得して、金融領域の型も高い次元に持っていきたいと思っています。ぼんやりだけど!
一方で、「型」だけ身につけても現場で通用しなければ自己満足で終わってしまいます。型どおりに展開しない面談になった途端に、何もできなくなってしまってはいけません。
「型」の限界を破るために必要なのが、ポータブルスキルです。中でも、各種思考系のスキル(ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング、アナロジー思考、デザイン思考……など)は、質の高いキャリア支援を行うにあたって、力になるものと思います。
たまに、キャリアコンサルタントやコーチングの資格を持っているわけではないのに、キャリア支援ができているなと思う人を見かけますが、それはポータブルスキルが長けているのだと私は見ています。
型だけではなく、実践の場でも価値のある対話体験を届けるために、これらの思考力、自分の頭で考える力を磨いていかねばなりません。

いずれにしても、ご縁があって出会った人に、キャリアについて考えるための良質な体験を提供すべく、日々精進していこうと思います。
まとめ CC2級に合格して
今回の合格は、10年以上前の成功体験を捨てることによる学びと習慣のアップデート、キャリア支援者としての学び戦略の整理、自身のスキルアップなど、多くの収穫がある体験となりました。
改めて、対話をはじめとするキャリア支援は面白く、追求したくなる仕事であると感じます。これからも頑張って参ります!
キャリア相談をお受けしています。ご興味を持っていただけましたら、一度お話ししましょう!
お申し込みは以下をクリック!
お話聴きます(おすすめ)
コーチングセッション
キャリアコンサルティング
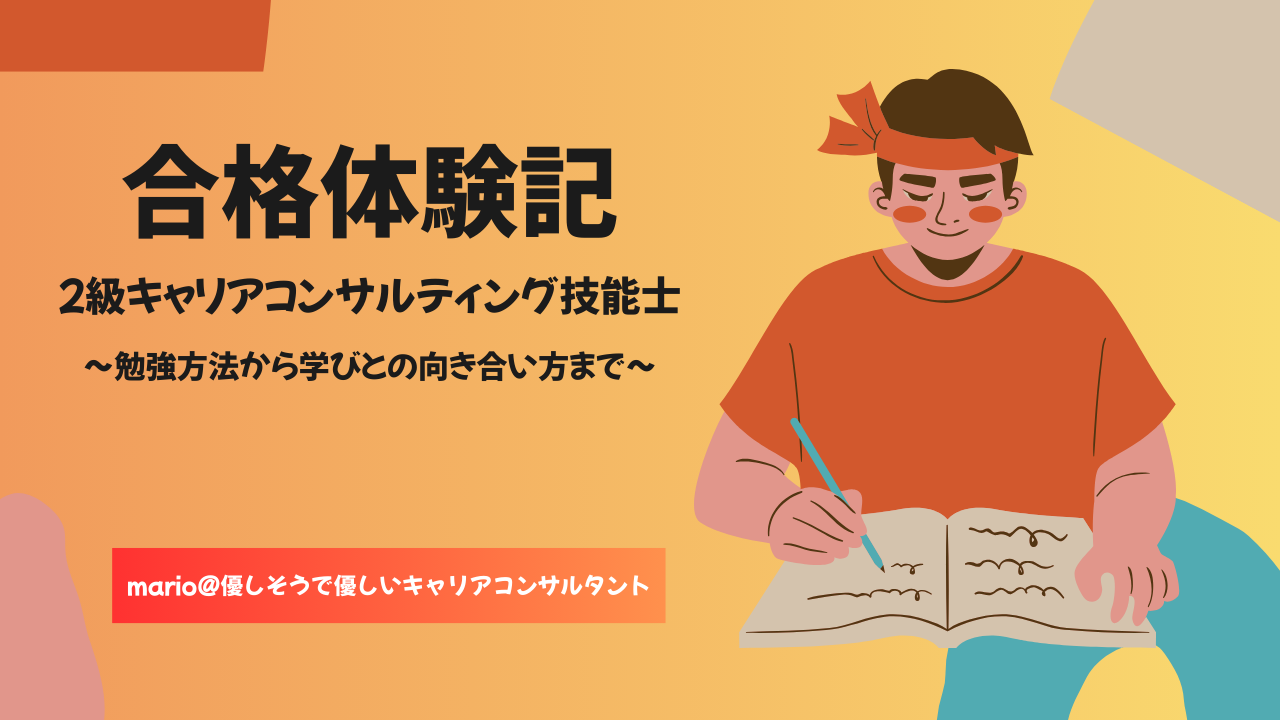





コメント